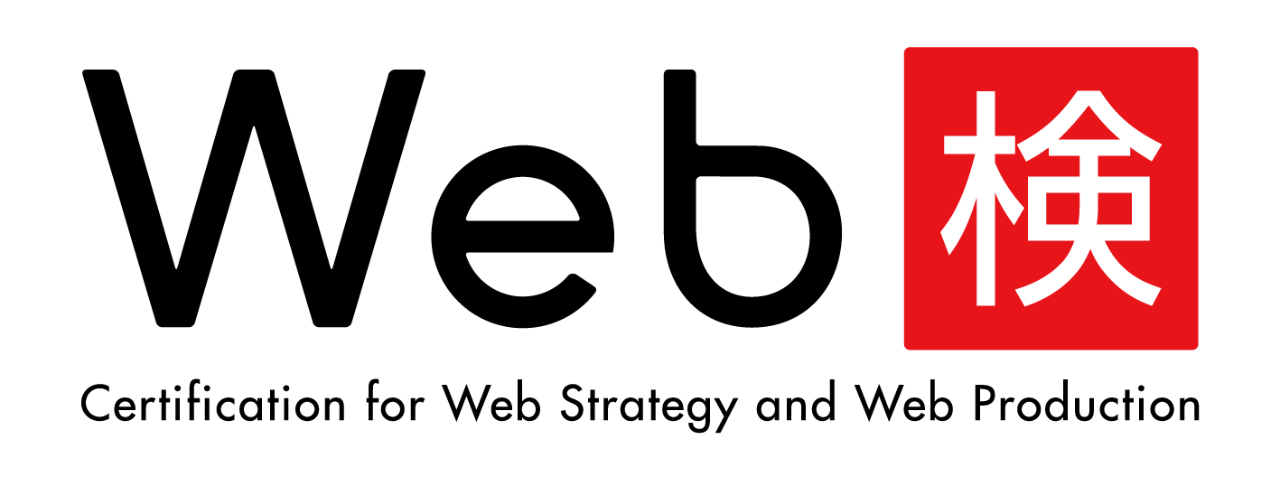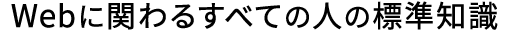お知らせ
第1回 Web検定 Webリテラシー(一斉会場方式)申し込みについて
第1回 Web検定 Webリテラシー(一斉会場方式)のお申し込み受付は終了しました。12月1日(土)より随時試験方式の予約を開始します。随時試験方式は12月16日(日)から受験可能です。随時試験方式の案内ページをご覧ください。
一斉会場方式の第1回試験のお申し込み、及びその後の流れは下記のとおりとなります。
お申込み
一斉試験のお申し込みの詳細は、企画協力・運営の日本出版販売のWebサイトにて行っていただきます。
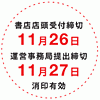
書店からのお申し込み
申込受付書店で受験料をお支払の上、「受験願書」と「書店払込証書」を同封してWeb検定運営事務局へご郵送ください。

郵便局からのお申し込み
Web検定専用の「払込取扱票」をご利用の上、郵便局にて受験料をお振込みください。

インターネットからのお申し込み
企画協力・運営の日本出版販売のWebサイトにてお申し込みください。
受験票の発送
2007年12月上旬発送予定です。
未着、または記載事項に誤りがあった場合は、お問い合わせ期間中に「Web検運営事務局(日本出版販売株式会社内)」へご連絡ください。
| お問い合わせ期間 | 2007年12月10日(月)〜12月14日(金) 10:00〜17:00(土・日・祝日を除く) |
|---|---|
| お問い合わせ先 | Web検運営事務局 東京都千代田区神田駿河台4-3 新御茶ノ水ビルディング16階内 お電話:03-3233-4808 メール:info@kentei-ukektsuke.com |
試験当日
受験票の記載事項に沿って、受験地の指定会場にお越しください。お持ちいただく物は下記のとおりです。
- 受験票
- 筆記用具(HBまたはBの鉛筆、またはシャープペンシル、消しゴム)
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、学生証、社員証など第三者機関発行で氏名・顔写真が揃って確認できるもの)
結果通知について
2008年1月下旬までに、全受験者へ合否通知をいたします。
合格者には、資格登録証をお送りいたします。
Web検運営事務局について
Web検運営事務局とは、一斉会場方式の試験について、社団法人 全日本能率連盟登録資格「Web検定」を主催するワークスコーポレーションから業務委託を受けた日本出版販売(日販)、および日販アイ・ビー・エスによる事務局です。
Web検運営事務局
101-0062
東京都千代田区神田駿河台4-3
新御茶ノ水ビルディング16階内
お電話:03-3233-4808(10:00〜17:00 土・日・祝日を除く)
メール:info@kentei-ukektsuke.com