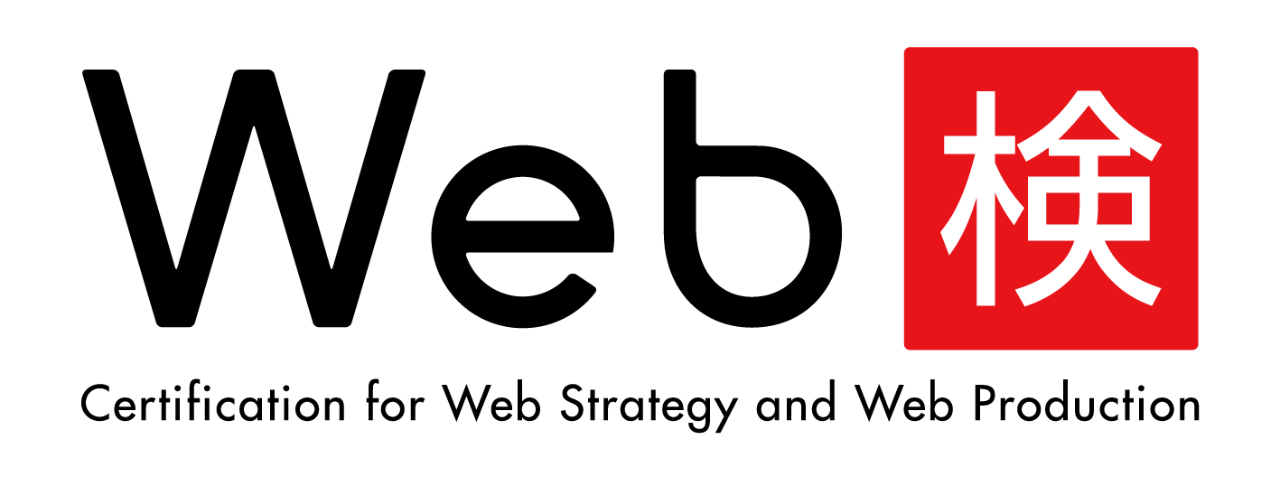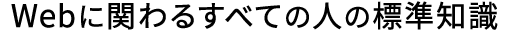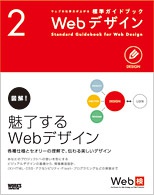お知らせ
標準ガイドブック3 Webディレクション 9月21日発売
各種の仕様に準拠し、かつ魅力的なユーザー体験をもたらすWebサイト・サービスを構築するには、制作工程管理はもちろん、要件を導き出すための現状分析〜プロジェクト企画、サイト全体の情報構造設計、集客施策立案〜実施まで幅広い専門知識・スキルが求められます。
これらのマネジメントについて、国内最大級のWeb制作企業がいかに大規模案件を成功させてきたか、現場での取組みから蓄積されたノウハウを体系化した、「ウェブの仕事力が上がる 標準ガイドブック3 Webディレクション」が9月21日に発売されました。
こちらの書籍から、「Web検定認定 Webディレクター」向けの検定試験問題を出題予定です。

ウェブの仕事力が上がる 標準ガイドブック3
Webディレクション
価格:本体2,838円+税
判型:A5正寸
総ページ数:264ページ
発売日:2007年9月21日
ISBN:978-4-86267-014-4
立ち読みする | 購入する
標準ガイドブック制作プロジェクト
プロジェクトメンバーにつきましては、こちらのページをご参照ください。
執筆者
マーケティング、広告、モバイル、情報アーキテクチャなど、各分野の国内キーパーソンの方に実務ノウハウを提供いただきました。
| 益子貴寛 | 株式会社サイバーガーデン 代表取締役 |
|---|---|
| 細川英樹 | IMJビジネスコンサルティング株式会社 コンサルタント |
| 野口貴史 | IMJビジネスコンサルティング株式会社 コンサルタント |
| 長澤大輔 | 株式会社アイ・エム・ジェイ リーダープロデューサー |
| 山本聰 | 株式会社アイ・エム・ジェイ チーフディレクター |
| 原一浩 | 株式会社エフエックスビイ 代表取締役CVO |
| 樋口進 | IMJビジネスコンサルティング株式会社 シニアコンサルタント |
| 佐藤伸哉 | 株式会社ビジネス・アーキテクツ/IA Institute 日本代表 |
| 横堀直之 | ネットイヤーグループ株式会社 インフォメーションアーキテクト |
| 坂本貴史 | ネットイヤーグループ株式会社 ディレクター/インフォメーションアーキテクト |
| 浅野紀予 | メディアプローブ株式会社 インフォメーションアーキテクト |
| 中嶋文彦 | 株式会社CCCコミュニケーションズ 事業戦略部 部長 |
| 渡辺隆広 | 株式会社アイレップ サーチエンジンマーケティング総合研究所 所長 |
| 吉田直樹 | 株式会社IMJモバイル プロデューサー |
| 境祐司 | 学校法人阿佐ヶ谷学園 高度情報化研究所 eface lab. 所長 |
| 長谷川恭久 | フリーランス Webデザイナー/Podcaster |