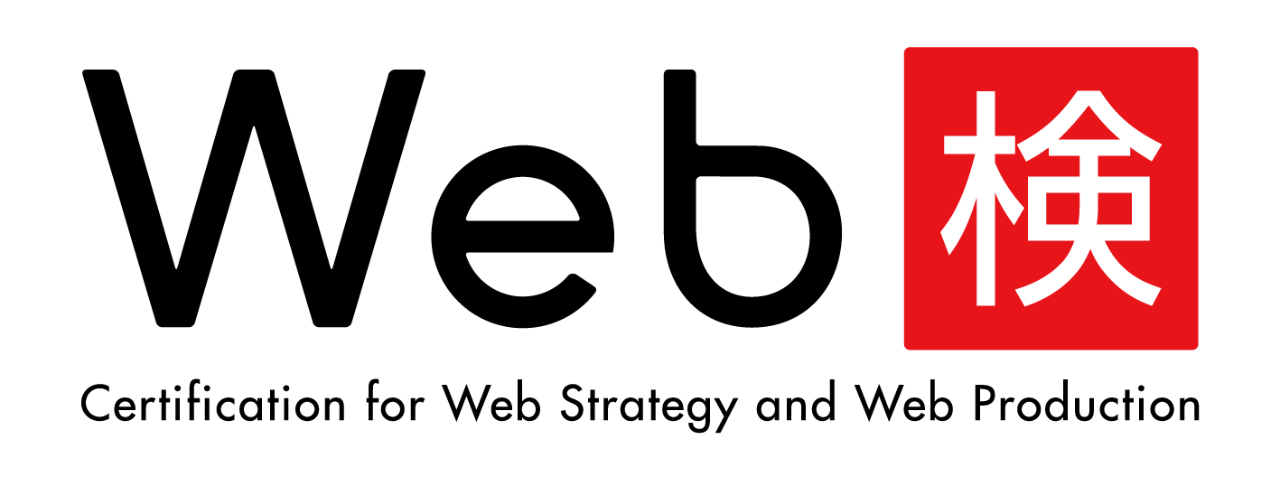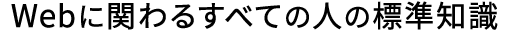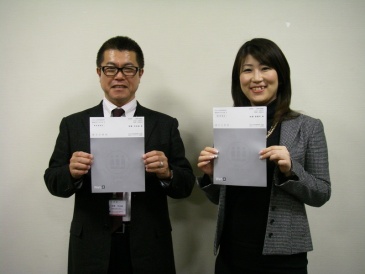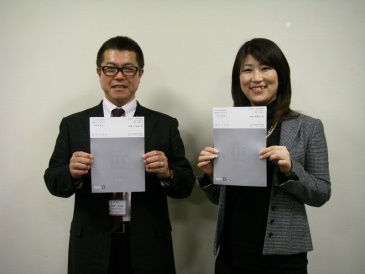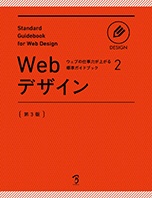Web検定(ウェブケン)
広告代理店に求められるWebの知識とは?
以下:
田実 日出翁さん → 田実
杉浦 奈保子さん → 杉浦
Web関連業務に特化した組織ができた背景は?
田実:私自身はメディアのプランニング業務を担当し、7~8年前からWebサイトやネット広告も手がけていました。クライアントの要望に応えるための技術や手法としてWebの分野に力を入れていく必要性が高まり「Webソリューション局」というWeb関連業務に特化した専門部署を立ち上げたのが2年ほど前。それまで各部門ごとで行っていた業務を集約したことで、情報共有と業務の効率化を図ることができました。
Web検定「Webリテラシー」との出会いは何ですか?

WEBソリューション局 アカウント推進部部長 田実 日出翁さん
田実:お付き合いのあるクリエイター専門の人材紹介会社担当者から『ウェブの仕事力が上がる標準ガイドブック1 Webリテラシー』(以下、Webリテラシー)という書籍を紹介いただいたのがきっかけです。
専門部署とはいえ、メンバーは各部門でWebに携わっていた者や、中途採用者の比率も高いため、実務経験はあるが、知識に偏りがあるのでは?と感じていました。参考になる書籍なども探していたのですが、マーケティングや制作技術など、ジャンルごとに解説したものはあっても、Webビジネスに携わる人に必要とされる知識を一冊にまとめたものはなかなか見つかりませんでした。
タイミングよく、資格試験にも対応した「Webリテラシー」を紹介され、幅広い分野の基礎知識が収められているため、このような書籍をきっかけに、もう一度勉強し直すことで知識の見直しができると考えたのです。
杉浦様は中途入社をされたそうですね

WEBソリューション局 メディア推進部メディアマネージャー 杉浦奈保子さん
杉浦:約一年前に中途入社で「WEBソリューション局」に配属されましたが、その前は米国のフリーペーパー制作会社でマーケティングを担当していました。そこで、フリーペーパーの情報を配信するWebサイトを立ち上げることになり、プロジェクトメンバーとして初めてWebサイトの企画・制作の仕事に携わることになりました。
Webサイトの立上げは成功し、広告枠の企画から営業のフローまで確立した段階で帰国しました。専門的な知識ではないものの、日常業務で身につけてきたものを活かしたいと考えて、今の職に就きました。
受験に対するみなさんの意識は?
田実:月1回の公式会議の場で、部のメンバー全員に「Webリテラシー」と「Web検定」について話をしました。管理職の立場としては、正しい知識を習得してもらうことこそが重要だと思いましたが、資格取得という目標がある方が勉強の励みにもなると考えました。
受験については、会議の中で希望者を募ったのですが、ほぼ全員が挙手。各自で「Webリテラシー」書籍を購入して勉強をはじめました。
杉浦:実は……私は皆が挙手したので「全員受けなければならばないの!?」と、雰囲気にのまれ手を上げたのが本音です。周囲のメンバーは自分よりも経験が豊富なため、受験までは危機感を感じて勉強しましたが、実は、彼らの方が逆にプレッシャーを感じていたようですね。
「Webリテラシー」を勉強して感じたことは?
杉浦:私自身、特別な勉強をする時間もなく、日常業務として身につけてきた知識であったため「Webリテラシー」を読みはじめると、実は基本的な技術や言葉の定義など知らない部分もあり、非常に勉強になりました。
また、発注する立場として実務で携わっていた分野は、スムーズに読み進めましたが、デザイン・実装などの分野は苦戦しましたね。今回勉強したことで、感覚的にわかっているつもりでいた制作会社がどのような業務を行っているのか、どのような技術があるのかなど、明確に理解できました。
勉強方法や苦労した点について教えてください
杉浦:Webサイト上に公開されていた練習問題を手がかりに、試験問題の予想をしながら本を読み進めました。知らない用語をノートに書き写して、後で繰り返し復習できるようにして覚えました。
田実:ヤマがはりにくい試験でしたね。満遍なくすべての分野から出題されますし、これから勉強される方も大変でしょうね。ただし、だからこそ価値のある試験なのではないでしょうか。
Web検定に期待することを教えてください
杉浦:始まったばかりの新しい資格ですが「持っていてよかった!」と思える資格になるとよいと、同僚と話をしているんです。Web検定の今後に期待しています。
田実:「Webリテラシー」については、広告代理店の営業であればWebメディアが専門でなくとも、勉強しておくべき内容ではないでしょうか。
また、私は「Web広告研究会」の幹事として、Webプロデューサー育成プロジェクトを推進しているのですが、ベースとなる知識のないままにWebサイトの運営業務に携わっている方も多いと感じます。クライアント側・運営者の立場の方々も、基本的な知識の土台を作り上げていくために「Webリテラシー試験」を有効に活用されるとよいと思っています。